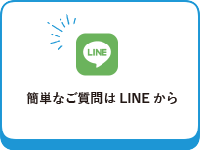2025.06.26
発達障害の特性のあるお子さまの「コミュニケーション力向上」のために
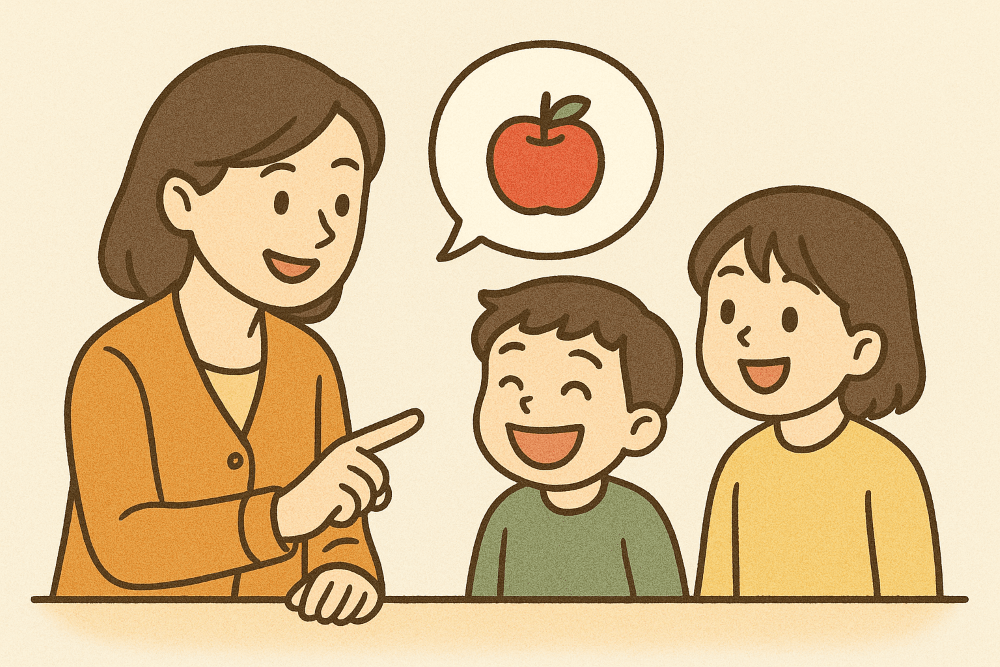
こんにちは。アルペン清和です。
お子さまの発達について、「ことばがうまく出ない」「お友だちとうまく関われない」といった、コミュニケーションに関するお悩みを抱える保護者の方は多くいらっしゃいます。
今回は、発達障害の特性のあるお子さまのコミュニケーション力をどう育てていくかというテーマで、私たちが大切にしている支援の視点と取り組みについてご紹介します。
発達障害とコミュニケーションの関係
発達障害の特性のあるお子さまは、自分の気持ちや要求をうまく伝えられなかったり、相手の言葉や表情を読み取ることが苦手だったりすることがあります。
これは「やりたくない」「関心がない」ということではなく、情報の処理の仕方や注目の仕方に特性があるためです。
たとえば、「指さしたものに注目する」「相手が見ている方向に一緒に注目する」といった、“相手と関心を共有する力(共同注意)”が育ちにくいことが、やり取りの難しさの背景にあることもあります。
こうした特性を理解したうえで、無理なく自然な形でのコミュニケーションを増やしていくことが、支援の出発点となります。
アルペン清和の取り組み - 日常の中で育てるやり取りの力
アルペン清和では、お子さまの発達段階や興味に応じて、コミュニケーション力の向上につながる支援を行っています。
①「いっしょに見る・いっしょに感じる」体験から
言葉のやり取りだけでなく、「同じものに注目する」「相手と視線を合わせる」といった、非言語的な関わりを丁寧に積み重ねていくことが第一歩です。
たとえば、「電車が通ったね」「見て見て、りんごだよ!」など、子どもの注意に寄り添った声かけを行い、やり取りのきっかけを増やしていきます。
②興味をベースにした遊びの中で
子どもが好きな遊びに入り込み、「同じ活動を一緒に楽しむ」中で、自然なやり取りが生まれます。おままごと、車遊び、パズルなど、活動に合わせて「ちょうだい」「どうぞ」「ありがとう」などの短いやり取りを促します。
③表情や言葉に気づく力を育む
遊びの中で、「〇〇ちゃん、笑ってるね」「いま、びっくりした顔だね」などの声かけを通じて、相手の気持ちや表情に気づく力を育てていきます。これは将来、相手の意図を読み取る上でも大切なステップになります。
ご家庭と連携した支援で効果を高める
支援の場での取り組みがより効果を発揮するためには、ご家庭との連携が欠かせません。アルペン清和では、定期的な面談などを通して保護者の方に家庭でできる関わり方のヒントもお伝えしています。
たとえば…
- お子さまが注目しているものに「それおもしろいね!」と反応する
- テレビや絵本を見ながら「どれが好き?」「同じの見てるね」と声をかける
- うまく伝えられたときには、「上手に言えたね、すごいね!」と肯定的に返す
こうした関わりの積み重ねが、「人と関わるって楽しい」という感覚を育て、日常の中でもコミュニケーションが自然に増えていきます。
「ことばが苦手」でも、コミュニケーションは育つ
「発達障害があるから、ことばでのやり取りは難しいのでは…」と不安になることもあるかもしれません。
しかし、コミュニケーション力とは“話す力”だけではありません。 視線、ジェスチャー、声のトーン、表情など、さまざまな手段で「伝える・受け取る」ことができるのです。
そして、相手と関心を共有する力が少しずつ育ってくると、それにともなって言葉も育ちやすくなります。 共同注意のような初期のやり取りが、発話への架け橋となるケースも少なくありません。
アルペン清和で、お子さまの成長を一緒に見守りませんか?
アルペン清和では、お子さま一人ひとりの特性や得意・不得意を丁寧に把握しながら、その子に合った方法でコミュニケーション力を引き出す支援を行っています。
「言葉が遅くても、他者とつながる力は育つ」――私たちはその可能性を信じ、日々の関わりを積み重ねています。
ご見学や相談も随時受け付けております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
お子さまの「伝えたい」「わかってほしい」という気持ちが育つように、一緒に歩んでいきましょう。